飲食系&福祉系企業のWebマーケターとしての実践経験を積み独立。Web歴10年以上でSEO歴5年以上の実績を経て、複数企業様の専属SEOアドバイザー&コンサルトを行っています。
また、現役のSEO講師としても活躍中。私、野田太陽(ノダタイヨウ)のプロフィールの詳細と過去の実績は運営者情報をご確認ください。
AI(人工知能)の発展に伴い、淘汰もしくは代替されていく職種があるという噂を耳にしたことのある方もいるのではないでしょうか。
先に結論からいうと、弁理士がAI(人工知能)に代替される可能性は低いとみられています。
本記事では、AI(人工知能)の発展による弁理士の将来性について考察しています。
ぜひ、最後までご覧ください。
弁理士の仕事内容は?AI(人工知能)に代替される?
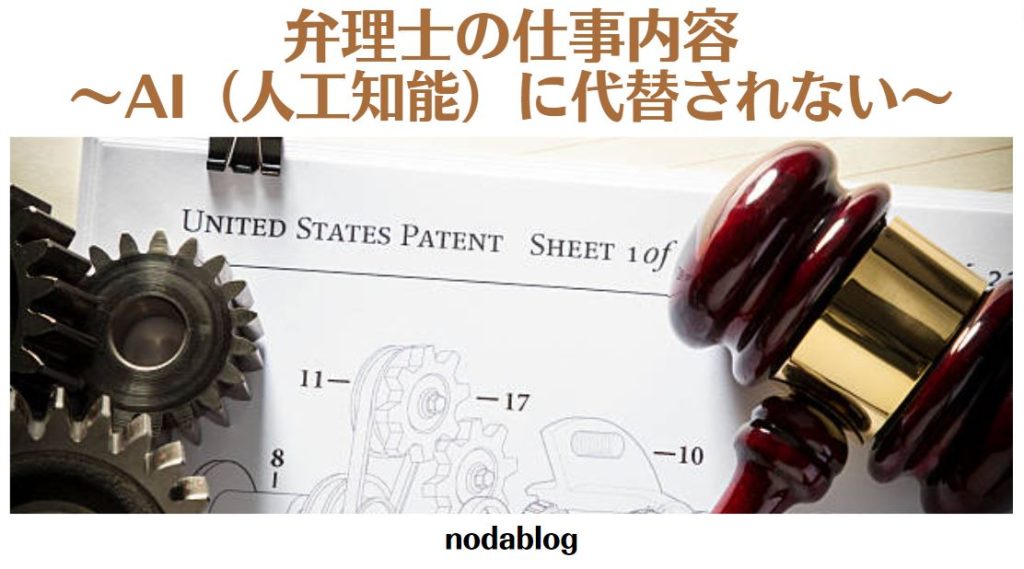
将来的に、弁理士の仕事がAI(人工知能)によって代替されるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
結論からいえば、いくらAI(人工知能)の技術が発達しても、弁理士の仕事がなくなることはありません。
まずは、弁理士の仕事内容から確認していきましょう。
弁理士の仕事内容
弁理士の仕事内容には、主に下記の3つが挙げられます。
- 産業財産権の取得
- 産業財産権の紛争解決
- 特許に関連したコンサルティング業務
このように、企業や個人に対して特許に関連するコンサルティング業務を行うなかで、特許権侵害などのトラブルに対応します。
他にも、特許庁に対して新規の発明品の知的財産権を申請する業務も担います。
AI(人工知能)によって弁理士の仕事はなくならない
近年におけるAI(人工知能)の台頭により、弁理士の仕事が代替されるという噂を耳にしたことのある方もいるのではないでしょうか。
いくらAI(人工知能)の技術が飛躍したからといって、弁理士の仕事がなくなることはありませんのでご安心ください。
そもそも、特許技術における特許庁への審査事例も急増しています。
特許技術における特許庁への審査事例については、下記の記事で詳しく解説しています。
弁理士の仕事がAI(人工知能)に代替されない理由は?エビデンスから根拠を考察!

弁理士の仕事がAI(人工知能)に代替されない理由としては、現状の技術では役不足だという点が挙げられます。
日本弁理士会の見解によると、AI(人工知能)による弁理士への影響について、下記の5つのポイントで示しています。
- 「人工知能*弁理士」での検索
- 「人工知能×特許明細書」での検索
- 先行技術調査
- 特許明細書の自動作成ソフト
- 外国出願のための自動翻訳ソフト
いずれもAI(人工知能)の技術を活用すれば、効率化が図れる内容ばかりです。
しかし、日本弁理士会は、下記のように見解を示しています。
先行技術調査ソフトと自動明細書翻訳ソフトは数年以内に完成するのではないか。一方で、発明の詳細な説明については自動化の可能性が高いが,特許請求の範囲の作成はAI(人工知能)では無理ではないか。
日本弁理士会
つまり、日本弁理士会の見解としては、時期尚早ということが伺えます。
いくら早くても、数年後にようやく整備が整う考えです。
AI(人工知能)と弁理士が共存していく社会になる!今後は具体的にどう変わる?
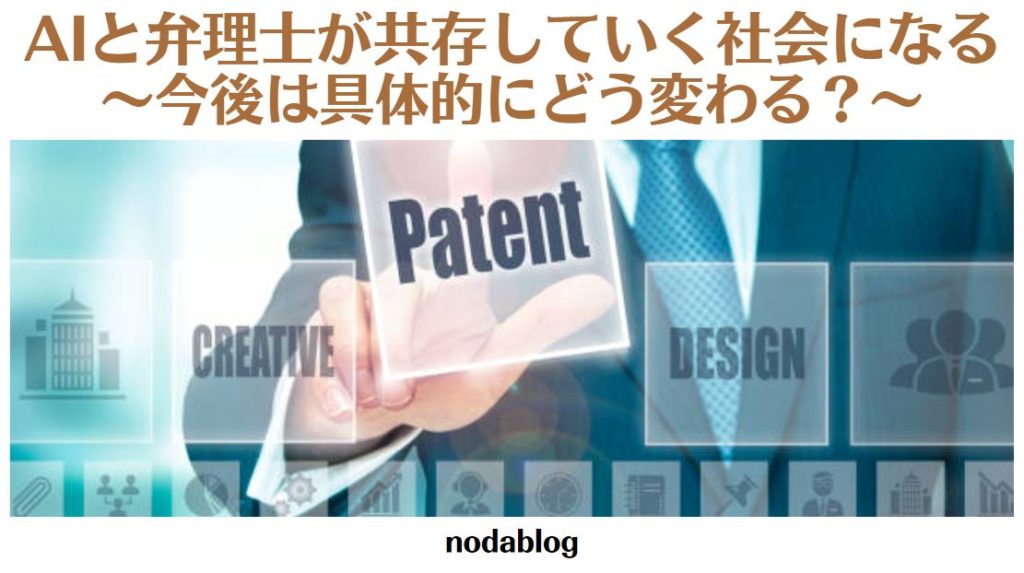
弁理士業界がAI(人工知能)によって、どのように変化していくのでしょうか。
日本弁理士会の考えについて、下記にまとめました。
- AI(人工知能)が進歩すると弁理士業務に大きな影響があり,特許出願や先行技術調査の依頼件数が減少すると予想される
- AI(人工知能)により浸食されにくい弁理士業務の必要性が示唆される
例えば、従来からある「出願代理の業務」に出願前後の業務を担うような仕組みを構築し,第3者を分離させずに一体の仕事として弁理士が引き受ける流れができるということです。
現状としては、AI(人工知能)の技術もまだまだ追いついておらず、弁理士の仕事が代替されることはありません。
しかし、それも近い将来、淘汰もしくは代替される流れも想定できます。
今後は、AI(人工知能)と弁理士が共存していく社会になることが予測されますが、弁理士としてAI(人工知能)活用術を磨いていくことが重要です。
まとめ|弁理士がAI(人工知能)に代替されることはない!
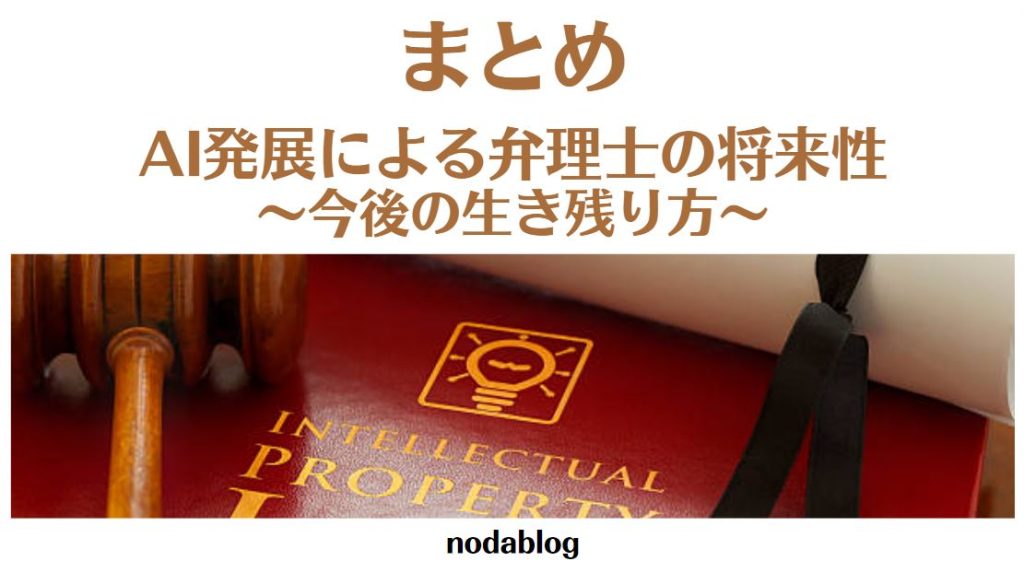
今回は、AI(人工知能)の発展による弁理士の将来性について、エビデンスをもとに考察してきました。
特許技術の躍進とともに、特許申請における需要も高まりをみせつつある昨今、弁理士という職種に注目が集まっています。
AI(人工知能)の技術向上により淘汰されている職種があるなかで、弁理士は顕著に人気を維持していることからおすすめの職種といえます。


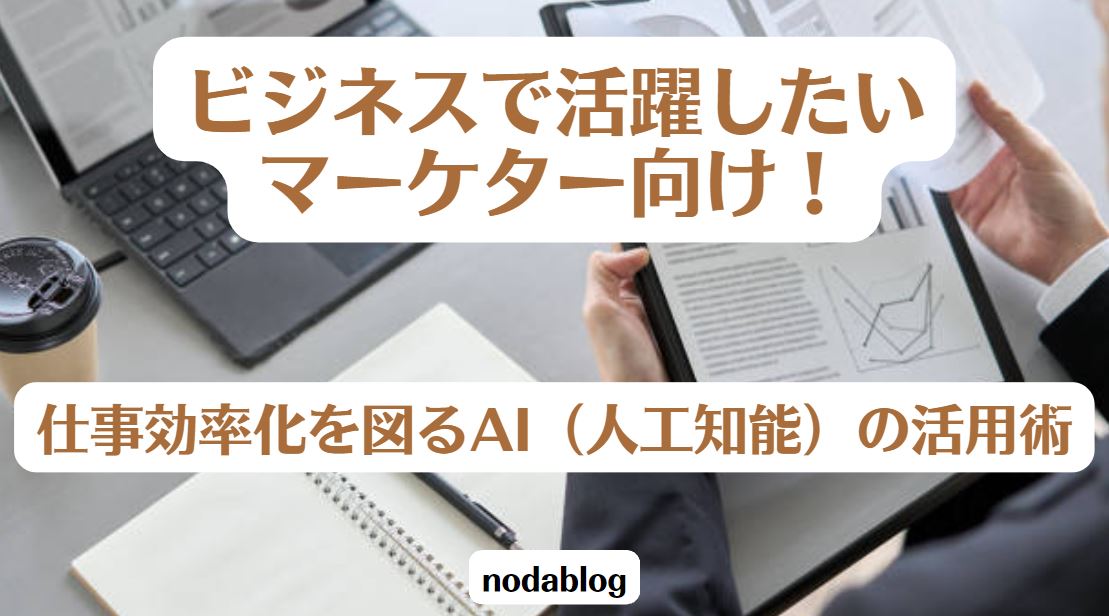
コメント